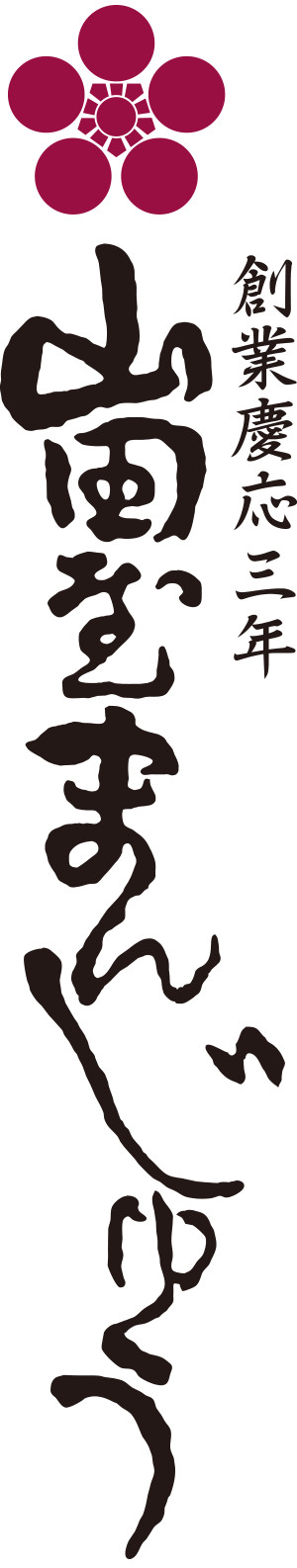新年明けましておめでとうございます。
皆さまにはおそろいで、
よいお正月をお迎えのことと存じます。
「正月三が日にいただく、ハレのごちそうはお雑煮です。
お雑煮は古くは「直会」と呼んで、
神様にお供えしたものを皆で分け合っていただくとても神聖な食事でした。
皆さんの地方では、どんなお雑煮をお召しあがりですか?
私どもが暮らす四国・伊予地方では、いりこ(煮干し)でとった出汁に人参や春菊を入れ、
蒲鉾を添えて、丸餅でいただきます。
関東は切り餅、関西は丸餅など地方によってさまざまですが、
年神さまの生命力を宿す鏡餅をいただくという意味で、
本来は丸餅だったとも言われています。
年のはじめに神社やお寺にお参りをする初詣。
もともとは大晦日の夜に、家長が寝ないで年神さまをお迎えする「年籠り」の慣習だったものが、大晦日の鐘つきと元旦の初詣の二つの行事に分かれたのだとか。
大勢が集まる有名な寺社へお参りするのもよいですが、地元の神社へ詣でたり、
恵方の方角にある神社にお参りをする「恵方参り」もまた、由緒ある習わしです。
いかがですか、今年はご近所へ----。

はるか紀元前のこと。古代中国の王朝の暦では、一年の最初の月を「正月」と呼んでいました。
そして、時代も下がった六世紀ころ。
仏教などとともに中国の暦法が、朝鮮半島の百済を経由して日本に伝えられます。
そのとき中国にならって一年の最初の月を正月と呼びならわすことになったと言います。
去年が暮れ、今年が明けると、新しい年の神さまが訪れるとされてきました。
その神さまが「年神さま」。
正月には、新年の恵方に恵方棚を設けて年神さまを祀ります。
お供えをするのは、注連縄、鏡餅、御神酒など。
また地域によっては、その年の豊作を祈願する正月行事も多く、
日本では、稲の一年と年神さまとの間には、深いつながりがあるとされてきました。
そして今年も、新たな年を迎えて、
田の恵みや種々の実りに深く感謝を払い、新しい年に祈りを捧げるのです。