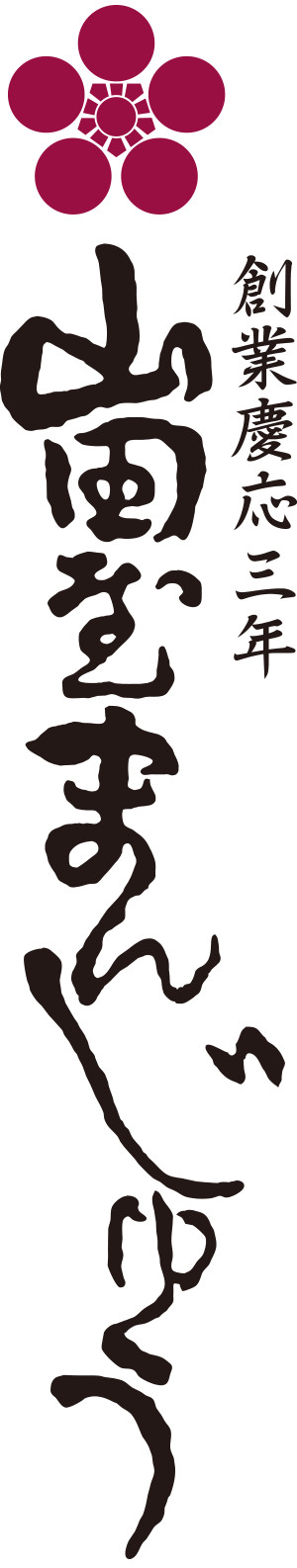冬。今年も収穫が終わり、
伊予の田畑にもしだいに北風が吹きつけます。
「冬」は、寒さに耐えて春を待つ季節。
冬の語源は、「冷ゆ」とも、寒さが威力を「震う」が転じたとも言われ、
さらに、生命力を呼び覚ます「振る」、
大地が振動して春を迎える「振ゆ」の意だとも言われます。
旧暦の十月は。そろそろ寒くなってきて、冬支度をする慣習がありました。
江戸時代、旧暦十月の最初の亥の日(今年は十一月十九日)にまず武家が、
第二の亥の日には町民が、「こたつ開き」をする日でした。
陰陽五行によれば、亥の日は水性にあたり、亥の日に火鉢や炬燵に火を入れれば
火事になりにくいのだとか。
茶の湯では、この日に炉開きをおこない、お菓子には小豆やささげを入れて表面を焼いた「亥の子餅」を用意するのだそうです。
猪が多産であることになぞらえて、子孫繁栄や無病息災を祈る意味もこめられています。
江戸の昔、新年を迎えるための諸々の準備は、十二月十三日から始まったと言われます。
それが「正月事始め」。城中でも町なかでも。この日になると煤払い(大そうじ)をおこない、
また「松迎え」と言って、松などの正月の飾り木や正月料理をつくるための薪を山に採りにいくのも、この日のならわしでした。
けれど師走の忙しさは格別で、大そうじはしだいに年末休みに入ってからするようになったのだとか・・・。