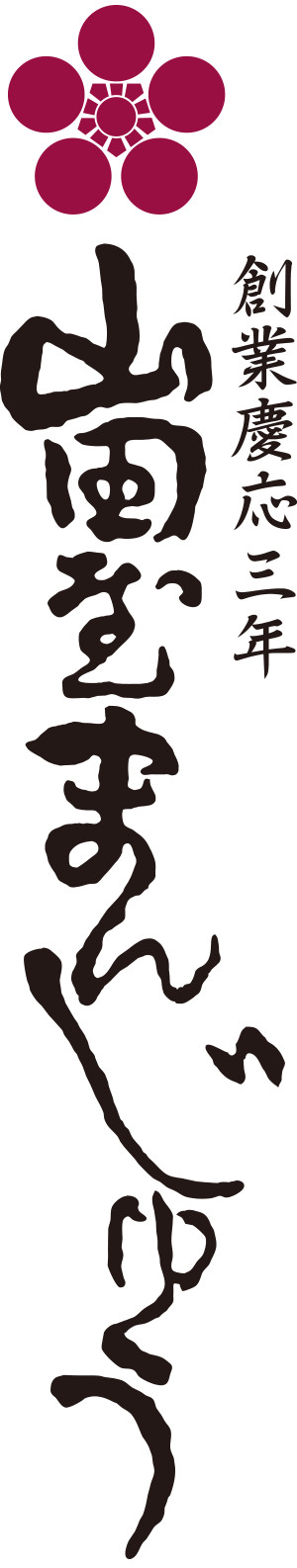夏。緑こぼれる稲田を
心地よい風が、吹き渡ります。
「夏」という呼び名は、一説には「撫づる」が語源だと言われます。
撫づる(現代語では「撫でる」)とは、ものに〈霊的な生命力〉を与える所作のこと。
田植えを終えて緑が映えるこの季節になると、田には、愛し児の頭をそっと撫でるような
爽やかな風が吹きわたり、
それにつれ、稲穂は日一日と育っていきます。
六月の晦日になると、各地の社では《夏越しの大祓》という半年に一度の祭りが行われます。
芽草で作った大きな輪が境内に立てられ、その下をくぐる茅の輪くぐり。
このとき、に切った紙を手で撫でて輪をくぐり、その人形を神前に納めると、
病気や邪気を祓うことができると信じられてきました。
《撫づることで、夏を迎える》のです。

私ども伊予の里山にも、一年のうちでもっとも生命感みなぎる夏が到来します。
虫も花もすっと身を伸ばし、持てる生命を謳歌します。
そして、旧暦七月十五日は、祖先の霊をお迎えし、もてなしてお送りするお盆の行事。
仏壇や精霊棚に飾る盆花は、祖霊が宿る依り代とされました。
桔梗や女郎花、鬼灯などが代表で、故人の好きな花が供えられます。
人の暮らしに《生命》がいちばん接する季節。それが「夏」なのかもしれません。