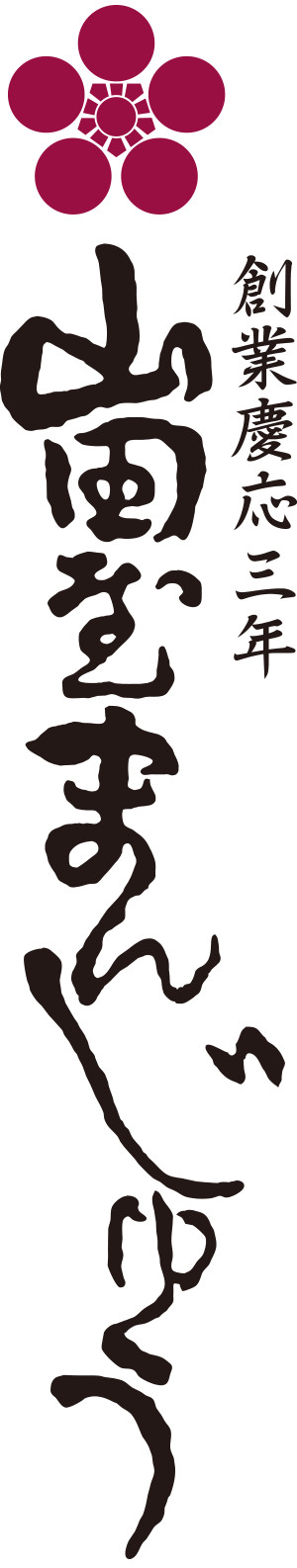秋。恵みを告げる黄金色の風が、
伊予の田畑を走り抜けます。
「秋」は、大いなる実りの季節。
秋という語の由来もそこにあって、
稲を刈り上げたあとの田の「空き」とも、
稲も草木も「赤らむ」のアキとも言われます。
そんなさまざまな光景がかさなりあって、
一年でもっとも美しい季節が織り上げられていきます。
九月九日は、平安時代に中国から由来した陰陽思想による「重陽の節句」。
そもそも奇数は陽の数で、なかでも九は最も大きな陽の極み。
九が二つ重なることから「重陽」と呼ばれたのですが、
奇数が重なると逆に気が強すぎて不吉なため、
邪をはらい長寿を祈る節目の日になったといわれます。
またこの日は、霊力の強い菊を飾って楽しみます。
この時期、各地で菊人形展が開かれるのもそのためで、
かつては、菊の花びらを摘み、天日干しをしたものを詰めた「菊枕」を贈り物にする典雅な習慣もあったそうです。
秋も深まると、日本各地で田畑の恵みに感謝する収穫祭がおこなわれます。
収穫の時期がまちまちなので、節句のように全国共通の日にちはありません。
私どもの伊予では、それを「亥の子祭り」と呼んで、(*旧暦十月上旬の亥の日のこと)
男の子たちが漬け物石ほどの石に四~五本のロープを結んで囲み、
歌をうたいながら、お餅つきのように石で地面を搗くのです。
恵みを授けてくれる大地を鎮め、田の神様に豊年を感謝する、 そんな大切な意味があったようです。